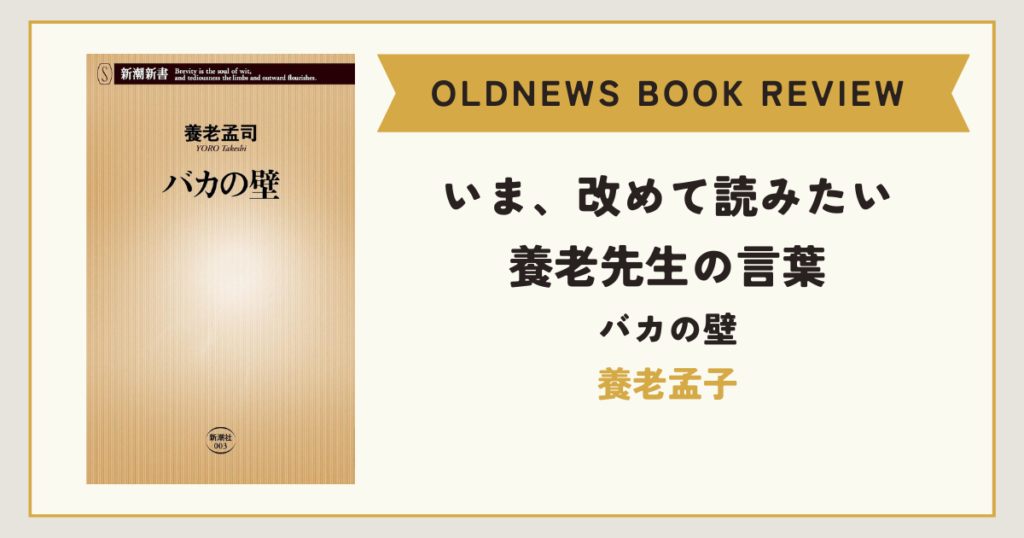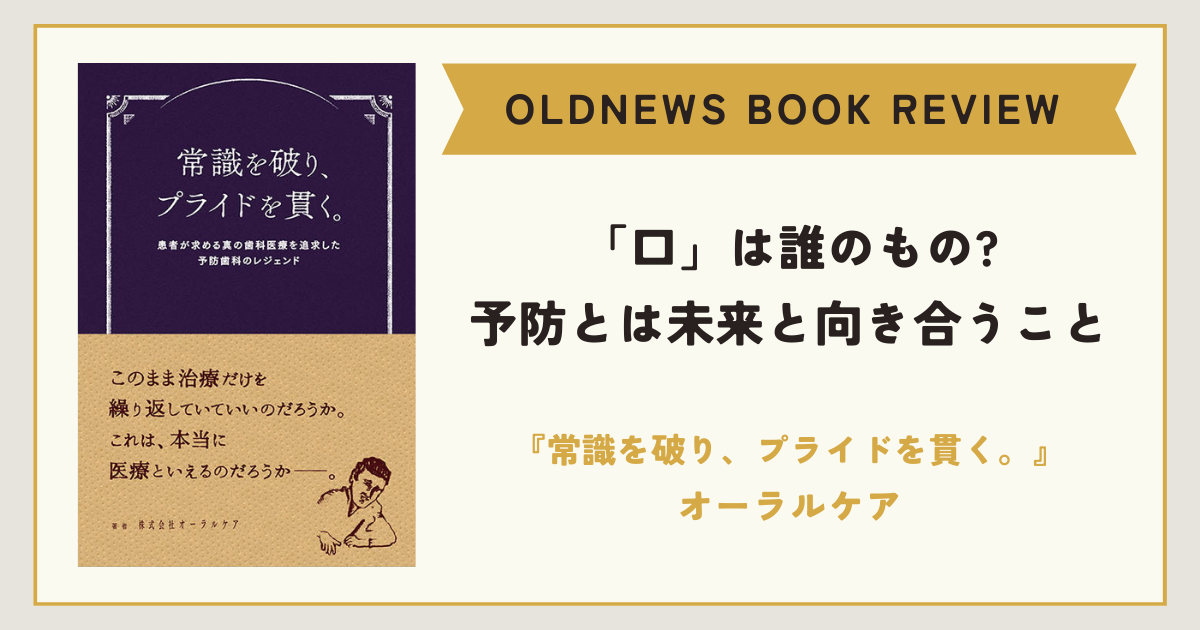
「自分の歯は何本?」
「自分の歯についてどんなことを知っていますか?」
そのようなことを聞かれても、大半の方は「虫歯の有無」「歯科医院の定期的な検診の有無」「毎日の歯磨きの実施の有無」といった二元論的な発想に陥りがちなのではないでしょうか。
恥ずかしながら、私もその一人でした。
身体の一部であるにもかかわらず、「痛みが出たら歯科医院に行く」という他人任せの考え方では、誰の口腔なのかが分かりません。
もちろん、医院に行くことは非常に重要であり、治療でしか取り除けない痛みや病気もあります。それでも「あまりに他人任せが過ぎるのではないか?」と。
本書を読むことで、自分の口腔に対する見方が少しばかり変わります。歯は歯科医院のものではなく、自分のもの。「自身でも考えるべきではないか」と気づかされます。

治療ではなく予防
歯科医院に行くことはすなわち「治療」を目的としていることが大半だと思います。こと、日本ではその意識が強いと思われますが、それは、1960年代のアメリカも同様でした。
本書の“主人公”である「ロバート・フランク・バークレー」氏は、1950年頃にキャリアをスタートさせた歯科医院で、治療で“一山”を築きました。来る日来る日もひたすらに患者を治療し、最新鋭の技術や設備を自身の医院に取り入れることで成功を収めていました。
しかし、成功の陰にはぼんやりとした不安もあったようです。治療後、数か月後もすると治療したはずの患者は悪化した状況で医院に戻ってくるのです。一人二人でなく、大勢の患者です。そのような状況に、後悔や疑念を抱くようになります。
「果たして治療だけが正しいアプローチなのか」。
疑念を抱いていたのは、バークレー氏だけではありませんでした。最先端の治療も貪欲に取り入れて“高品質”の治療を施すバークレー氏の医院は財をなす一方で、「治療費が高額すぎる」という批判も受けるようになり、地元で開業していながらも、友人すらもだんだんと敬遠するようになっていました。
ある日、古くからの友人であり4人の子を持つ女性の患者が彼のもとに治療にやってきました。
お子さんが多いこともあり、バークレー氏は彼女の金銭的な負担を考慮して「最低金額」の治療計画を作成し、次回の来院を待ちました。…しかし、その女性は約束の日にバークレー氏の医院を訪れることはありませんでした。
その後、偶然にも街で彼女を見かけたバークレー氏。なんと彼女は別の「安い」医院で義歯をいれるべく、「すべて」の歯を抜いてしまっていたようです。
当時、30歳を過ぎたばかりで、実はバークレー氏にとって学生時代の憧れだった姿はそこにはなく、バークレー氏は大きなショックを受けました。
質の高いはずの治療の無意味さと自身の無力さを反省したのでした。
「必要なことは治療だけでなく、治療が必要になる状態にならないことではないのだろうか…」
バークレー氏はこれまでの自身の活動、ひいては医療者としての人生を見つめ直します。
「重要なことは『予防』なのではないだろうか。予防を実践すれば歯を抜くこともなく、金銭的にも低コストで健康を保てるのではないか」
そう考えた彼は予防に目を向けます。これが世界の歯科における「予防」の始まりでした。

予防で何をなしえるか
バークレー氏はその後、医師や心理学者から学びを受け、患者さんとのコミュニケーションを図りながら一人ひとりに口腔ケアの方法や重要性を伝えていくようになります。
果たして予防とは何か。本書では、自身の口腔と向き合い、考えることだと説かれています。
私自身「痛くなったらケアをする」という発想から「毎日のケアを短時間でも適切に行う」という生活に切り替える努力をするようになりました。
毎日の積み重ねに勝る健康維持の方法がないことは十分に知り得ながらも、歯については疎かになっていました。
歯が無くなることは当たり前のことではない。そんなことを改めて感じるとともに、予防とはつまり、自身がよりよく生きる一つの手段だと考えさせられます。
自分の口腔と向き合うきっかけをくれる素敵な本です。

投稿者プロフィール
最新の投稿
 BOOK2024年4月26日【HABIT 「習慣で買う」のつくり方】「習慣脳」と「判断脳」。私たちは無意識に行動する
BOOK2024年4月26日【HABIT 「習慣で買う」のつくり方】「習慣脳」と「判断脳」。私たちは無意識に行動する BOOK2024年2月6日【ホビットの冒険 下】「みなさん、ひげをどうぞすりへらさないように」
BOOK2024年2月6日【ホビットの冒険 下】「みなさん、ひげをどうぞすりへらさないように」 BOOK2024年1月25日【ホビットの冒険 上】ファンタジーはいくつになっても楽しい
BOOK2024年1月25日【ホビットの冒険 上】ファンタジーはいくつになっても楽しい BOOK2024年1月22日【絵本とは何か】絵本とは「子ども」も「大人」も心から楽しめるもの
BOOK2024年1月22日【絵本とは何か】絵本とは「子ども」も「大人」も心から楽しめるもの